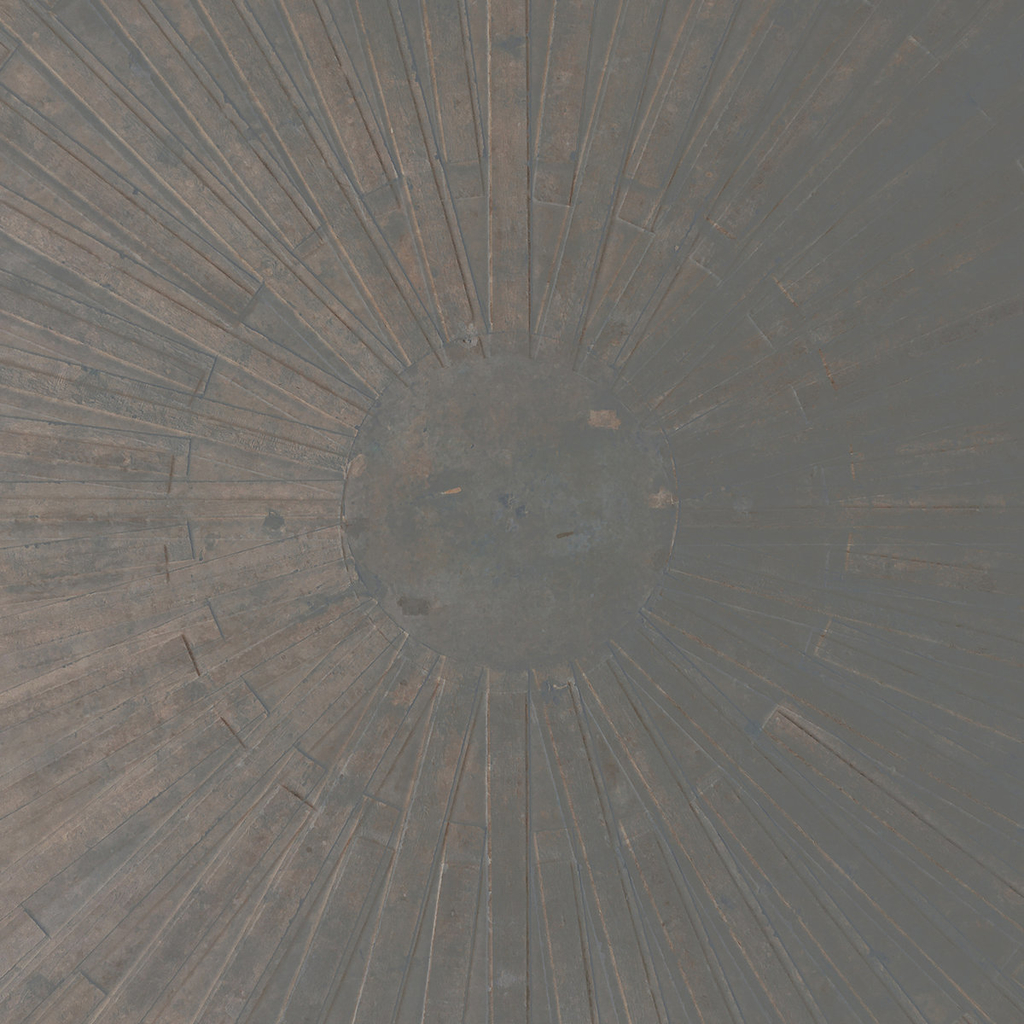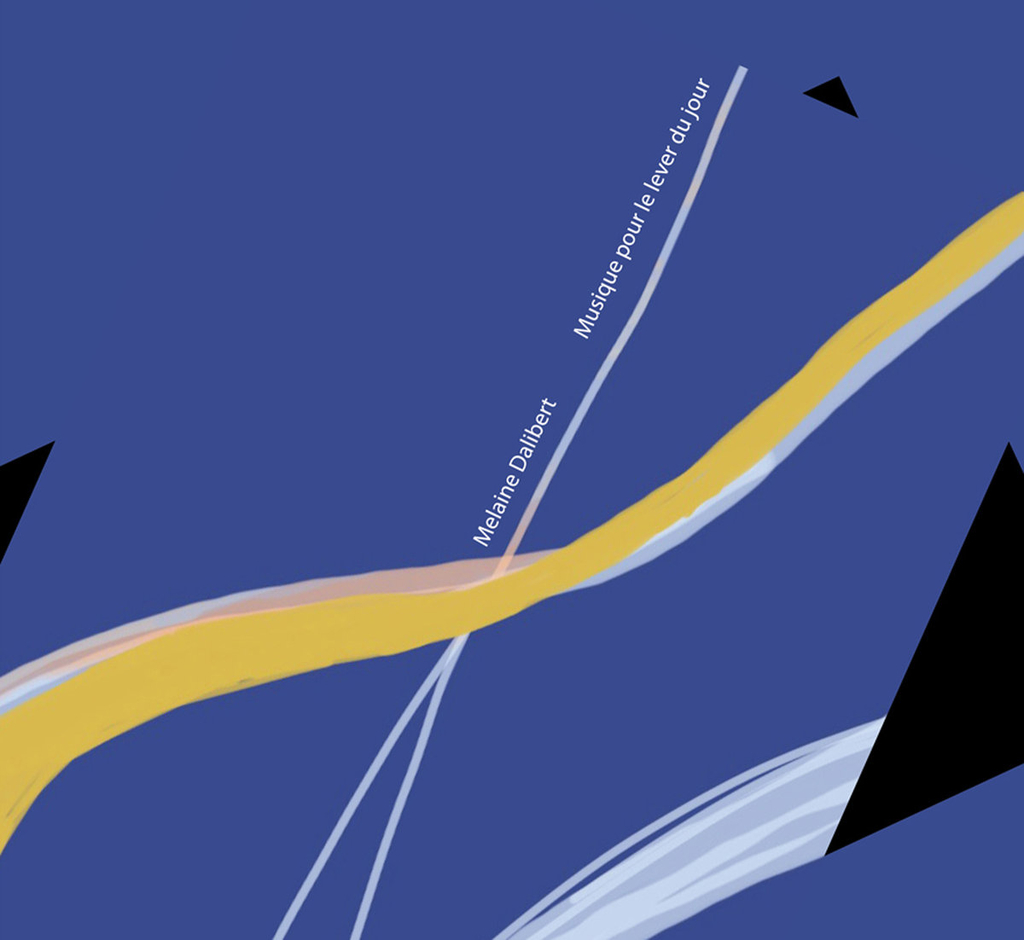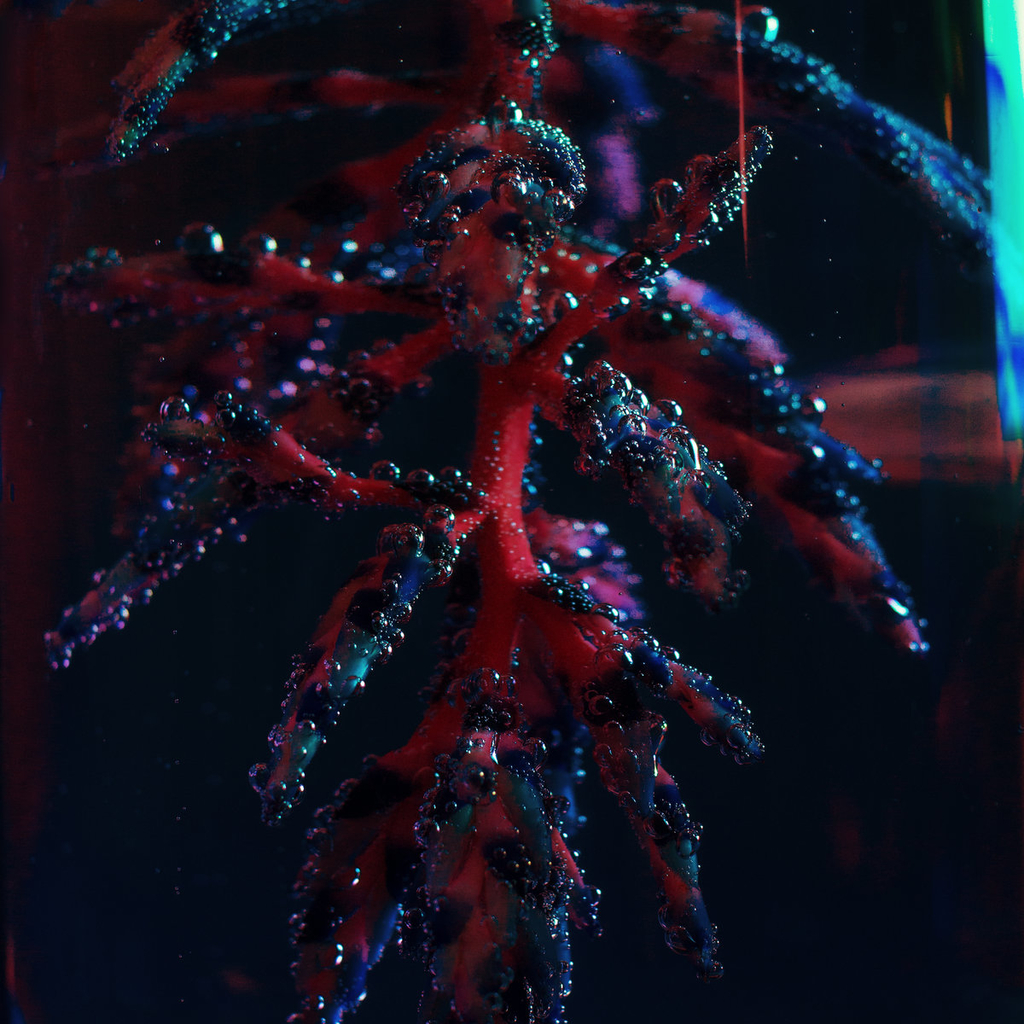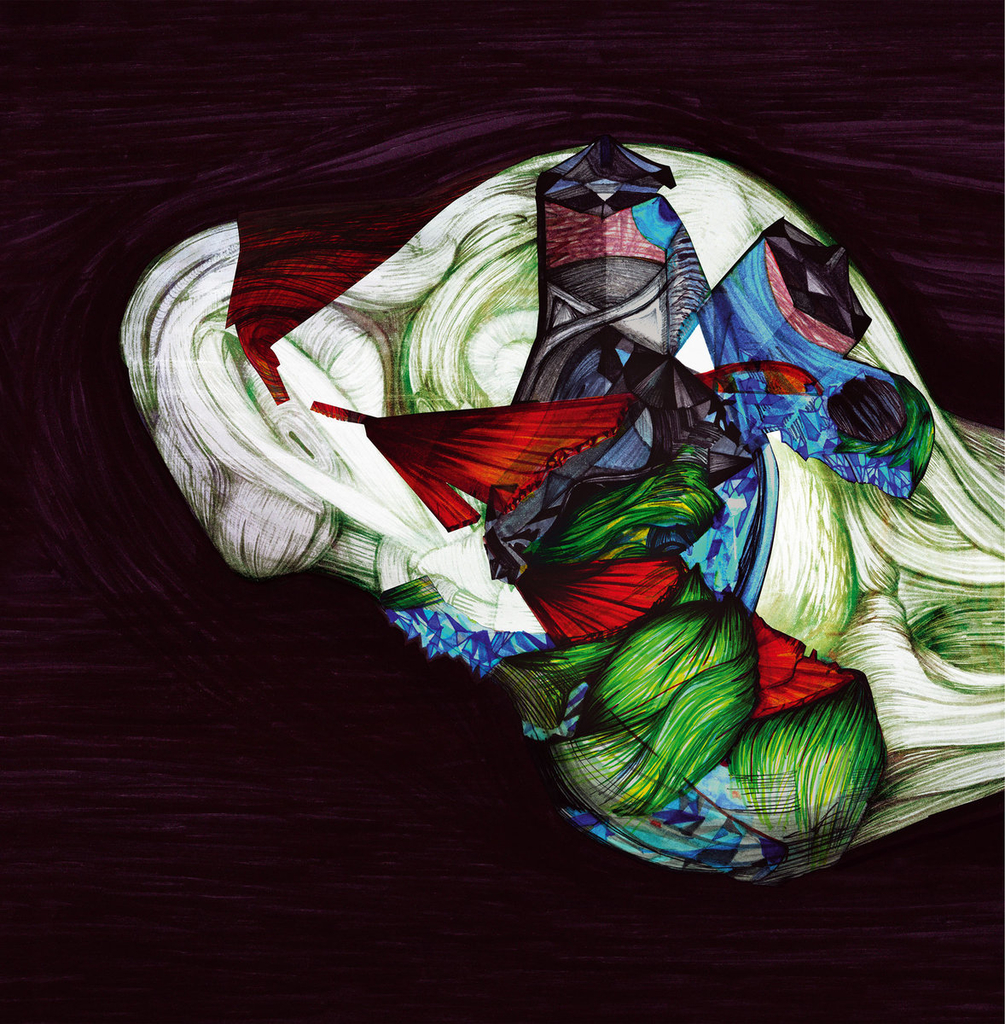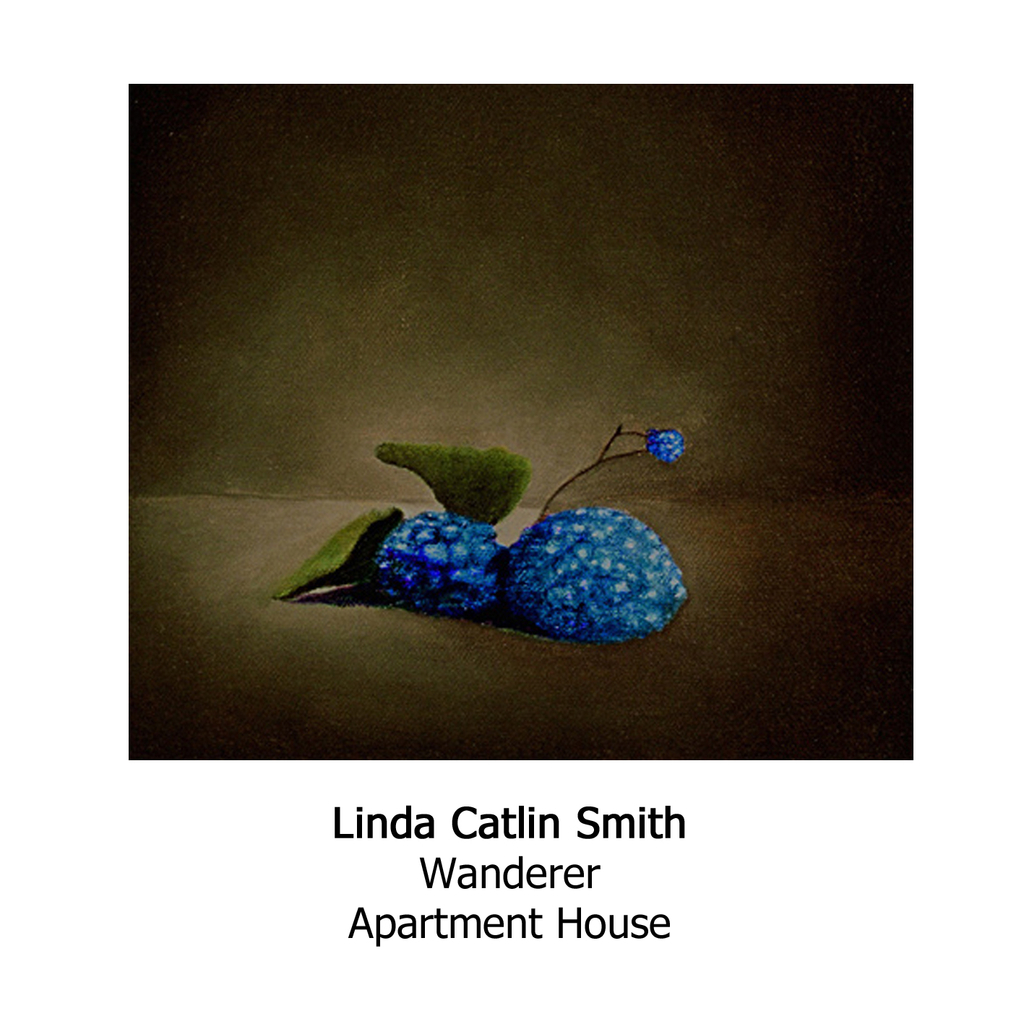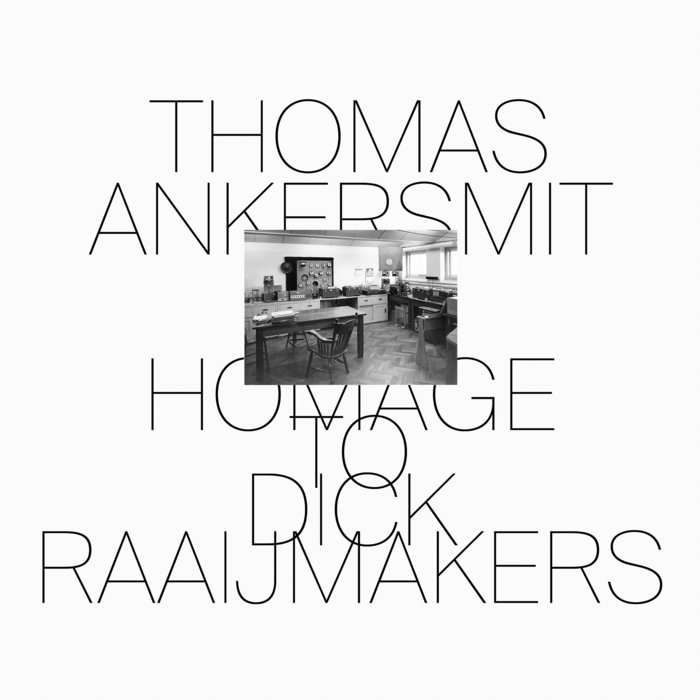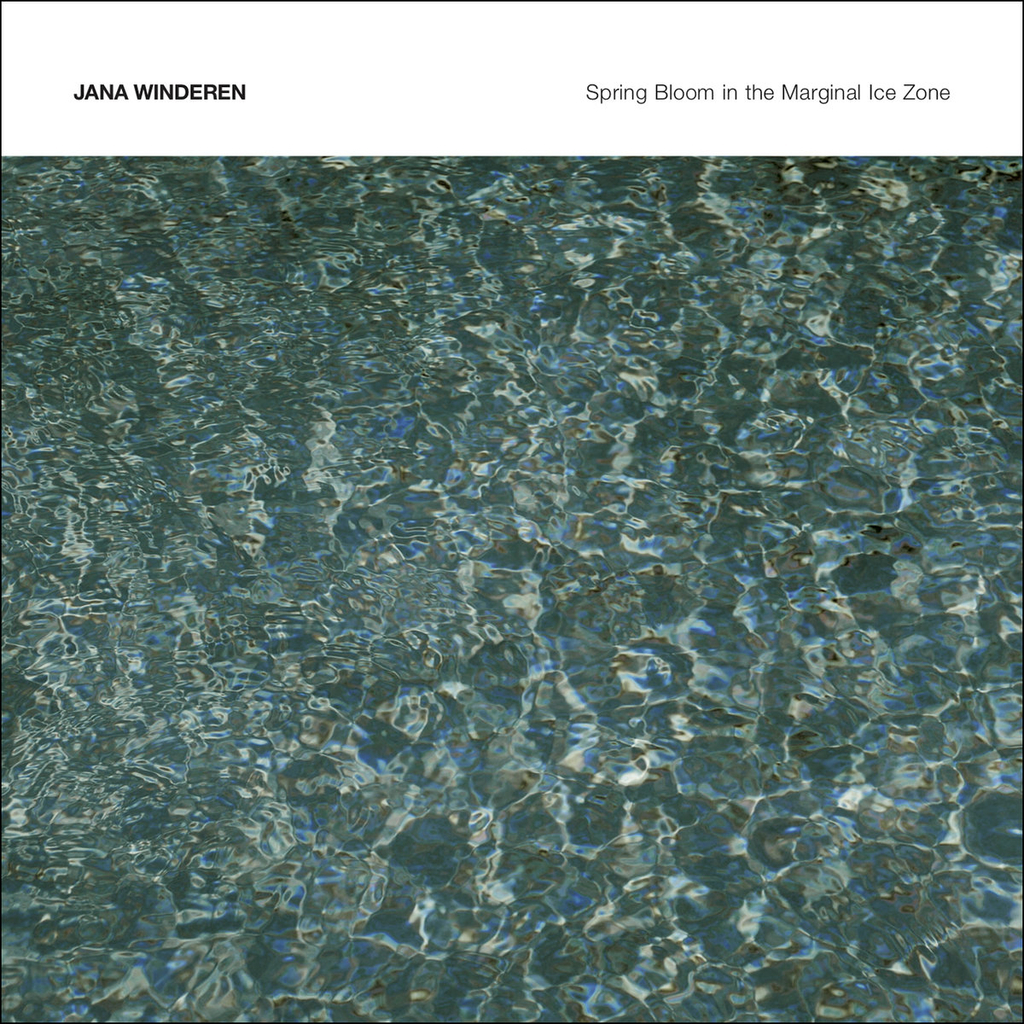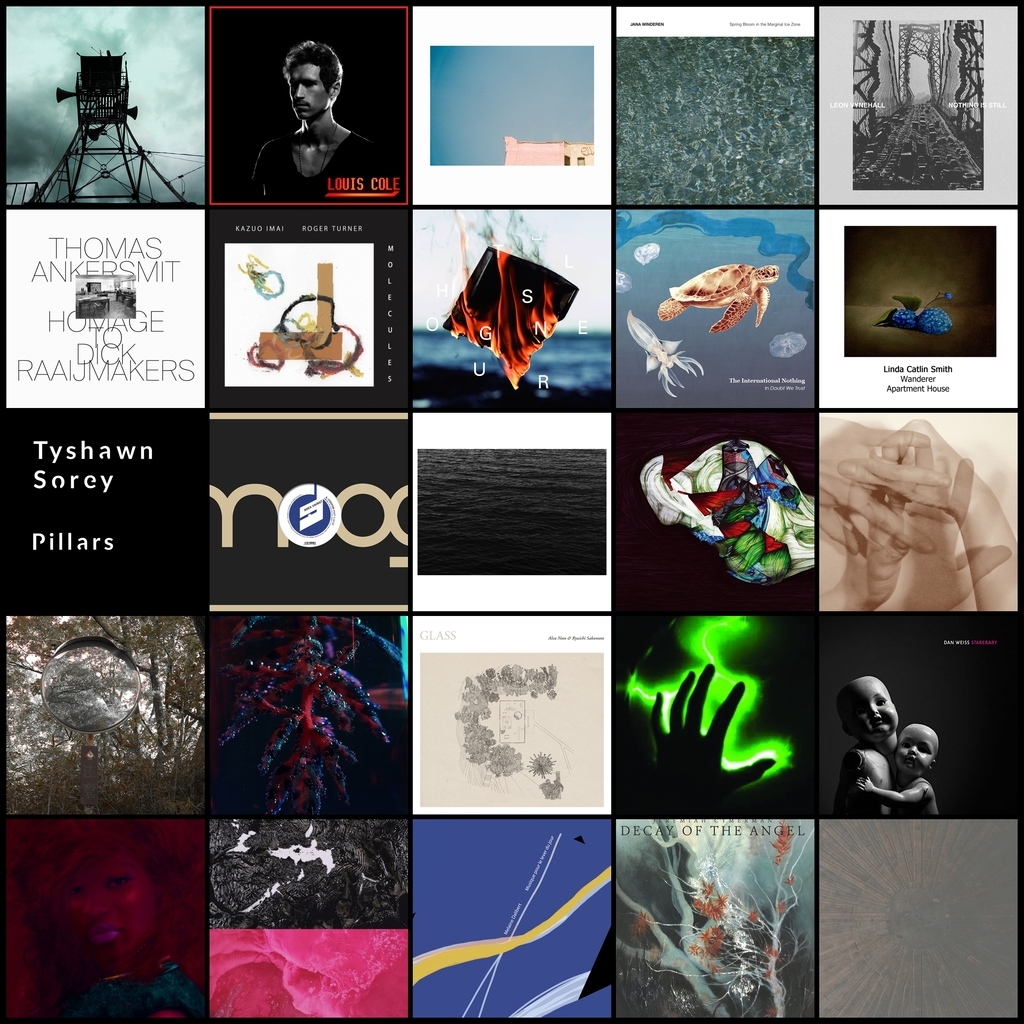
遅くなりましたが2018年の年間ベストです。25作選んで順位を付けました。カウントダウン方式なので順位が上のほうだけ見たい方は目次から飛んでください。画像をクリックすると試聴などが行えるページへ飛べます。ページ最下部にはプレイリストもあります。文章中の「今年」は2018年として読んでください。ではどうぞ。
25~21
【25】William Basinski + Lawrence English『Selva Oscura』
アンビエント/ドローン。アメリカの音楽家ウィリアム・バシンスキとオーストラリアのローレンス・イングリッシュというアンビエント~サウンドアートなどの領域で活動する二者の共演作。2018年はここ数年は以前ほど毎日のようにはやらなくなっていた寝る時に音楽かけっぱなしにするのを再び結構な頻度でやるようになったんですが(そういうのまとめたツイートがこちら)、これもそんな感じでよくかけた一枚。とりたててここが新しいとかっていうポイントはない気もしますが、引き伸ばされたハーモニックなドローンとくぐもったノイズの層が作り出すほどよく曇った音像が心地よく、とてもいい感じに意識を遠のかせてくれます。今更言うまでもないですけど、やっぱこういうアンビエント/ドローンは好きですね。なくては生きていけない。
【24】Jeremiah Cymerman『Decay of the Angel』
インプロヴィゼーション/多重録音。NYを拠点にクラリネット奏者、サウンドアーティスト、レコーディングエンジニアなどとして活動するジェレマイア・サイマーマンの作品。彼は僧院でインド音楽にふれあいながら育ち、エレクトリックベースの演奏やメタルやハードコアのバンドから音楽活動をスタート、後にクラリネットを始め更に専門学校でオーディオエンジニアリングを学んだという変わったキャリアの持ち主で、レコーディングスタジオを主要な作曲ツールとして扱い、クラリネットの即興演奏と電子的な操作やプロダクションを拮抗させたスタイルでアルバムを制作しています。本作においてもクラリネットの演奏を中心に据えながら、多くの時間でそこに空間系から音響をノイズ化するような過激なものまでの多様なエフェクトやオーバーダブ、クラリネットでカバーできない低い音域の電子音などが加えられ、個人の音楽家としての足取りがつぶさに反映されたドゥーミーで荘厳な世界観を描き出しています。表面的な音楽の形式こそ異なりますが、演奏家やインプロヴァイザーとしての顔と同時にDAWなどのラップトップ環境も含めた現代的なスタジオツールを用い総合的に音楽を作るプロデューサー的な視点を強く感じさせる辺りは同年のラフィーク・バーティア『Breaking English』に通じるものがあると感じます。アブストラクトな即興演奏の形態を維持しながらここまで空間や景色を色濃く想起させる作品は珍しいですし、即興性の強い音楽のフィールドで活動する音楽家の中でも一風変わったヴィジョンを持った面白い存在に思います。
【23】Melaine Dalibert『Musique pour le lever du jour』
現代音楽。フランスのピアニスト/作曲家による長尺のピアノ作品。この人は昨年Another Timbreから出したアルバム『Ressac』も素晴らしかったですが、本作もそちらに収められている楽曲と傾向は近く、規則的な歩みを思わせるミニマルなリズムと、螺旋階段をイメージさせるような変化とも循環とも認識されるような音階の扱いが大きな特徴。そのうえでそこで用いられる音階がより和声的に透明度の高いものになっていて簡素な美しさが際立った内容になっています。Jurg Freyのピアノ曲にも通じる真っ白な部屋を思わせるような簡素な美しさのある音楽ですが、ハーモニー的な移ろいの頻度や音の足取りのリズムや間といった点で個人的にはこの人の音楽はより素直に馴染む感覚があって、いい意味で必要以上の緊張感を感じずに聴くことができます。Jurg Freyの音楽には音楽における “退屈さ” の発生や音楽が意識の内と外を行き交う存在であることをハードコアなかたちで見つめさせるという側面があるように思いますが(別の作品についてのものですが、こういった感覚を非常に詩的かつ端的に記しているのがこちらのページの山形一生さんの文章)、本作は後者の側面を柔らかに内包しつつ前者についてはそれをギリギリのところで巧みに避けようとする設計がなされていると感じます。この辺の意図の方向性やバランスもすごく好みですね。今聴き直しながらこれを書いてるんですが、思ってたよりも更によく聴こえてなんか順位もっと上でもいいかもとか思いつつ…。ちなみにアートワークはDavid Sylvianによるもの。
【22】Rafiq Bhatia『Breaking English』
ジャズを起点にインディーロックの分野などでも活動するギタリストによる作品。前作『Yes It Will』はヴィジェイ・アイヤー、ビリー・ハートなどが参加したエッジーなコンテンポラリージャズ作品でしたが、今作はDAWなどを含めた現代的なスタジオ環境の中で様々な楽器のサウンドと電子的なプロセスをかけ合わせ理想の音響を実現しようする、演奏家/作曲家としての自身も包括したトータルプロデューサー的な視点が強く反映されたチャレンジングな作品。②での歪んだ音の扱いや随所で聴かれる低い帯域からせり上がって来るような音響、⑦でのインダストリーな電子音と音響処理が施された器楽的音色の交錯などからは彼がフェイヴァリットに挙げるベン・フロスト、ティム・ヘッカーの強い影響が伺えますし、他にもレディオヘッドがインド音楽を研究したような④、重たいリズムの上でゴスペルのコーラスを思わせる声の層とエレクトロニックな音響が錯綜するR&Bライクな⑥辺りはなかなかないバランスの音楽になっていると思います。Untitled Medleyでメールインタビューを担当させていただいた経緯もあり今年特に聴き込んだ一枚。
【21】Demdike Stare『Passion』
テクノ/エクスペリメンタル。2018年のテクノ寄りのリリースではObjektと並んでかなりハマりました。この人たちの作る音にはマシニックなテクノ然としたものともハウス寄りのしなやかなグルーヴとも違った、例えでいうならポストパンクの人たちがやるファンクみたいなちょっとギクシャクしたグルーヴのかっこよさみたいなのがある気がするんですが、今作も全体的な音のザラつきだったり時にかなりぶっきらぼうに聴こえる音色の扱いやカットの仕方なんかがサグい魅力を放ってて最高。リズムの打ち込み方に関しては案外クラブミュージックの語彙に素直に収まってるように思いますが、そこに絡む音色との噛み合わせでこのフィーリングが出せるんだなと感心。なのでかなり素直にノレる音楽でありつつ彼らのサウンドの旨みも味わえるっていうかなり美味しいアルバムかと。
20~16
【20】Dan Weiss『Starebaby』
アメリカのドラム奏者/作曲家によるメタルの影響なども取り入れたジャズ。メシュガーや初期のメタリカなどメタルのバンドが影響源として挙げられていて、リフの反復を多く用いた曲構成、ディストーションやファズの効いた歪んだ音色の多用などに反映されていますが、それらはダン・ワイスの音楽が以前から持っていた変拍子やインド音楽に習った周期の長いビートサイクルなどのドラマーらしいリズム面の工夫と巧みに接続、交錯されており、結果的にはプログレッシブロック的折衷感覚に基く得体の知れないミステリアスさを纏った音楽が奏でられています。こちらにレビューあります。
【19】Peter Evans『The Veil』
フリーインプロヴィゼーション/ジャズ。現在のインプロヴァイズド・ミュージックにおいて特異かつ優れたトランペット奏者として大きな存在感を発揮しているピーター・エヴァンスのソロ作。2018年はこの人目覚ましいほどの傑作を連発してきて本当に楽しませてもらいました。『Weatherbird』『Poisonous』『Syllogistic Moments』というそれぞれ異なる楽器の演奏家とのデュオ作も本当に甲乙つけがたい最高な内容なんですが、一枚選ぶとなるとやっぱソロに若干思いが傾くかなというなんか悔しいような心苦しいような心境でこれを選んでます。新たな奏法の開拓など具体的なことがわかるわけではないのですが、聴いた直感としては2016年のソロ作『Lifeblood』から更にパワーアップした印象あります(強いて挙げるなら2曲目のホーミー的にも対旋律を歌っているようにも聴こえるような声の用い方は新しく感じますし、細かなフレージングというより持続的な発音に電子楽器のツマミを回すような感覚で音色変化を加えていくような演奏においてより進歩が感じられる気がします)。ソロ作こそ丸二年ほどの空きがありますが、この人の参加作は結構な短いスパンで耳にしているんで飽きがきてもおかしくなさそうなところが、このソロ最初に再生した時はそのサウンドがバカみたいに新鮮に響いてきて驚き、いまだにこれだけ驚けることにも驚き。インプロをメインに活動する優れた演奏家には通じることかもしれませんが、たった一音でその人とわかる音色をそもそも持っているのはもちろん、この人はマイクを通した響きの活用や録音の質感にもかなり拘ってそうで、トータルでの響きの独自性が本当に強く、それがダイレクトに目一杯味わえるソロ演奏はやっぱちょっと反則級の快楽性があります。
【18】Alva Noto & Ryuichi Sakamoto『Glass』
電子音楽/アンビエント。ドイツのサウンド/ヴィジュアルアーティストと日本の音楽家によるコラボレーション作品。コネチカット州にある建築家Philip Johnsonのグラスハウスでのライブ録音。シンギングボウルやクロテイルの弓弾き、そしてグラスハウスの壁を擦った音などアコースティックな要素もあるようですが全体の印象としてはシンセの持続音の存在感が強いリッチな音色のアンビエント作って感じ。ライブ録音だからだと思いますがわりと展開が大味だったりダイナミクスも広かったりで、時間によっては結構迫力のあるサウンドになってます。大胆にリバーブのかかったリッチなサウンドをクリアな録音で切れ目なく味わえるっていうかなり “溺れられる” 度合が高い作風なんで例えばシューゲイザーの空間系で引き伸ばされたサウンドが好きな人とかも同じ感覚で聴ける部分あるかもしれません。2018年の初めのほうだったんで記憶は薄れてきてますが、夜中の長時間の運転の際にこれをひたすらリピートして聴いたのはなかなか印象に残る体験でした。坂本龍一はドキュメンタリー映画『CODA』の中で昨年の『async』についてや自身の理想とするサウンドの在り方としてタルコフスキー映画のサウンドへのシンパシーを口にしていましたが、自分としては『async』よりむしろこちらにそのような趣(惑星ソラリスの首都高のシーンでかけときたい感)を感じました。
【17】Objekt『Cocoon Crush』
エクスペリメンタル/クラブ。Objektは前作の段階でPANからリリースしてるアーティストの中ではクラブミュージックとしての機能性と音色やリズムの実験性のバランスがいい人って印象があって、反面それがちょっと器用貧乏的にも聴こえて自分はそんなにハマらない感じだったんですが、今作はヴェイパー以降アリになった感じの音色やコンクレート的なエディット感なんかまで本当に見事に取り込んでてそのバランス感覚のよさがめちゃくちゃポジティブに響いてくる仕上がりで驚きました。クラブミュージックとコンクレート的な音色のエディットの融合って2010年代にいろんなかたちで試みられたと思うんですが、完成度でいうとこれはかなり優れたものなんじゃないかと思います。なんか現代的なセンスでグリッチ/IDM的な音楽やったらこうなるんじゃないかみたいにも聴こえますね。Arca以降のディストロイドって形容されるような音楽のフィーリングもあると思いますが、それらの音楽で前面に出てきがちな喧騒性が抑えられてかなり丁寧かつクールな音楽って印象になってるのも個人的にはポイント高いです。
【16】Jim O'Rourke『Steamroom 42』
アンビエント/電子音楽。不和な色合いを随所で漂わせながらも起承転結がしっかり感じられる聴き応えのある1曲39分の作品。自然音の連なりを電子音でトレースしたような場面から不穏な色合いの弦楽器のようなサウンドが支配する場面、更に音楽的に安心感のあるハーモニーとそこに影のように重なるノイズや不和な音程が折り重なるようにして進むアンビエント的な場面へ展開していく、物語性のある音響合成物といった仕上がりで現在42作が出ているSteamroom作品でも特に完成度の高いもののように思います。瞬間ごとの細かなサウンドの変化と、より長いスパンで音楽の流れを見た時の情景の移り変わりが精緻に組み込まれている感じが本当に見事。特に26分以降が好きすぎる。スピーカーで大音量での再生が推奨されているんですが、それを行ってもかなり複雑かつ迫力のある場面でも粗が目立つ感じにならなくて、単純に音がすごくいいって部分にも驚かされます。
15~11
【15】Okkyung Lee『Dahl-Tah-Ghi』
ジャズや即興演奏の分野で活動するチェロ奏者によるソロ・インプロ作品。2013年6月、オスロのエマニュエル・ヴィーゲラン美術館で30人限定で行われたパフォーマンスの録音。非常に残響の豊かな空間のためか、その音響特性を確かめるように様々な方法の発音を用いた演奏になっており、特に12分辺りからの空間に傷を残すかのような激しいボウイング、そしてそれが徐々に消失していく様や、低音弦を弓で激しく弾いたり叩いたりする場面での残響の連なりによって膨張したような響きなどが凄まじいです。既発のソロ作『Ghil』などではディストーションなどの何らかのエレクトロニクスを用いたような歪んだ音色での演奏も行い、音色の変質を取り入れた演奏表現も得意としている彼女ですが、ここではその方向性が過激なかたちで押し出され、弦楽器のソロ演奏であることが信じられないようなサウンドが出てくる場面も多々あります。2018年はインプロの作品で自分にとって新たな視点をもたらしてくれる作品にいくつか出会えたのですが、そのうちの一つが本作で、今まであまりその魅力にしっかりコミットできていなかったチェロやコントラバスのソロ演奏という領域に、(かなり特殊な例であるとは思いますが)自分が面白がれる表現が存在するということを実感できたのはとても嬉しかったです。
【14】Pali Meursault『Stridulations』
サウンドアート/実験音楽。フィールドレコーディング的な手法を用いコンセプチュアルなサウンドアート作品を多くリリースしているフランスのアーティストPali Meursaultの作品。本作は虫の鳴き声と蛍光灯チューブの音(?)を用い自然と機械の間に存在する奇妙な音の親和性を探るといったコンセプト。サウンドアート的な作品に対しては、その表面的なサウンドを音楽的な価値判断で聴こうとすることはあまり褒められたものではないとは思いますが、これに関してはそのコンセプトの発生源が音色の性格というかなり音楽に近しいポイントにあるためか、そういった捉え方にも結構馴染む感じがしてすごく気に入りました。ブチブチッっと鳴る電子音のインパクトや、虫の鳴き声の持つ音色変化の周期と電子音のフィルター開閉やLFOのによるうねりの絡み合いなど、電子音楽的な視点から聴いて非常に豊かに感じられるサウンドが収められています。ノイズにしても持続音にしてもとにかくどれもがいい音色で鳴っているので、単純に快楽的な音響作品として是非聴いてみてください。
【13】Ryo Murakami『Sea』
アンビエント/電子音楽。ミニマルなテック・ハウスからそのキャリアをスタートし、近年は独自のドゥーム・エレクトロニクスな作風が注目を集めているRyo Murakamiが、自身のレーベルDepth Of DecayからLPのみでリリースした作品。電子音だけでなくピアノや弦楽器などのアコースティックなサウンドも効果的に用いた、アートワークそのままのモノトーンで小品的なアンビエント作品が収録されています。前述の作風で多用される重たく不穏な音色も随所に差し込まれますが、それらは音楽の静けさを脅かすことはなく心地よい緊張感をもたらす方向に作用し、作品全体の簡素でありながら安易さを感じさせないトーンを非常に強固なものにしています。今年聴いたアンビエント作品の中でも特に繰り返し再生した一枚。こういった色合いや緊張感を持った音楽でこれほどアンビエントとしての機能性も保持してるバランスのものはあまりないと思うので気になった人は是非手に取ってみてほしいですね。
【12】Mika Vainio『Lydspor One & Two (Blue TB7 Series)』
電子音響/エクスペリメンタル。2017年に他界したフィンランドのサウンド・アーティストのミカ・ヴァイニオが2015年に遺した録音のリリース。アメリカの電子楽器メーカーMoog Musicが所有するスペースMoog Sound Lab UKで製作された音楽を限定リリースするレーベルMoog Recordings Libraryのリリース第一弾でもあり、モジュラーシンセサイザーのSystem 55を用いて制作されています。自分はこれまで(それなりの数を聴いてはいるものの)決して彼の音楽のいいリスナーではなくて、音色の性質やその配置の間が生み出す緊張感などの個性はわかるもののそこに馴染み切れない感覚があり、ある程度の時間を切り出すと強く惹きつけられるもののアルバム単位で聴こうとすると途中で集中力が切れてしまうものが多かったのですが、今作は(表面上やっていることはいつもとそんなに変わらないように聴こえるのに)なぜかそういった部分がクリアされてすごく自然に入ってくる音になってました。彼の制作や演奏における機材構成を逐一チェックしてるわけではないですが、おそらく元々それほど規模の大きなシステムを扱うタイプではないこともあってか、本作におけるSystem 55を用いた制作は結果としていつもより音色のバリエーションが増えるという方向性に作用しているように感じられ、非常にモノトーンな印象の強い彼の作品の中では電子音楽/シンセサイズ・ミュージックとしての彩が豊かに感じられるのがおそらく大きなポイントなのかも。勿論前述したような緊張感を纏ったサウンド構成も十分に発揮されていて、ツールが変わろうとも揺るがない作家性の強さみたいなものも改めて意識させられました。やっぱこの人すごく特異な存在だったんだなと…。
【11】Tyshawn Sorey『Pillars』
ジャズ/即興音楽。主にドラマー/作曲家として活動するタイショーン・ソーリーの作品。これまでも長時間の切れ目のない演奏が目立ち、二枚組のアルバムも発表するなど大作指向の強かった彼ですが、本作もそれぞれ70分超の3つのトラックからなるトータル3時間半、CD三枚組に及ぶ長大な一作。編成も管楽器奏者2名、コントラバス奏者4名(うち1名はギターを、他の1名はエレクトロニクスを兼任)、ギタリスト1名、そして打楽器類の他に管楽器の演奏や指揮も行う自身を加えたオクテットという特異なものですが、終始全員が演奏に参加するのではなく場面によってソロやデュオなど人数や楽器の組み合わせは変化し、演奏の内容もそれに応じて完全にフリーな即興から特定の音の反復や持続に焦点が当てられた明確なディレクションが伺えるものまで幅があり、様々なグラデーションで即興と作曲の溶け合いが提示されます。収録された三篇からはメロディやリズムを書く作曲の域だけでなく、メンバーの音楽性を理解しそれを即興という方法の中で随時様々なパターンで重ね合わせながら見守るような、より巨視的な視点から音楽をコントロールしようとするタイショーンの意図も伺え、演奏者個々が自由に振る舞えるスペースを確保しつつひと続きの演奏の中で展開や音楽的起伏を生み出すために演奏者、作曲者、そして(演奏者の振る舞いに即時的に関わっていく)指揮的役割など様々な階層から音楽に携わるそのバンドリーダーとしての巨大な存在感が音楽全体を包み込んでいるように感じられます。この辺りはリンク先のキャプションでも名前が出されているブッチ・モリスやアンソニー・ブラクストンといった音楽家の即興性の管理や作曲という行為の解釈の拡張を促すような活動に連なっていくような姿勢を感じさせます(タイショーンはブッチ・モリスの考案したコンダクションを行うなどの活動もしています)。もちろんそういった音楽への関与の仕方だけでなく演奏自体も刺激的なものとなっており、特にドゥンチェン(チベット音楽に用いられる管楽器)やコントラバス4本から生み出される低音に比重を置いたドゥーム・ドローン的なサウンドや、タイショーンにとっては盟友といえるトッド・ニューフェルド、ベン・ガースタインとの緊密な演奏は大きな聴きどころです。
*演奏の細かなパートへの言及や感想はこちら
10~6
【10】Linda Catlin Smith『Wanderer』
現代音楽。昨年のベストに挙げた『Drifter』も素晴らしすぎたカナダの作曲家Linda Catlin Smithの作品。昨年のが2枚組でかなりボリュームのある作品集だったので今年も出してくるとは思いませんでした。しかもクオリティ的に全く遜色なくもしかしたらこの先より多くリピートするのはこっちかもってくらいの素晴らしい出来。音型の繰り返しなんかもありますし、音程の面でも平均律の調性音楽の範囲で作曲されていると思うんですが、リズムの面でもハーモニーの面でも絶妙に掴みどころがなく不安定に揺らぐような印象を与え、しかもそれが美しさとして伝わってくるような作品が並んでいます。かなり複雑で抽象的な音楽ではあると思うんですが、聴けば誰もが美しいと思うような場面がそこかしこに散りばめられているような音楽で、最初から最後まで同じテンションで気に入る人は少ないかもしれませんが(私も決してそうではありません)どこかしらで琴線に触れるところがあるはず。難しいイメージのある現代音楽ですが、その中でこの人はクラシカルな楽器と調性音楽の語法を比較的多く用いつつ聴き覚えのない音楽を作ってるタイプだと思うので、多くの人がそれぞれの知っている音楽と何らかの接点を見出しながら聴くことが可能な気がします。なのでいろんな人に聴いてみてほしいですね。特にピアノ&ヴィブラフォンと弦&管楽器がそれぞれ別の秩序で演奏しているような微妙に収まりの悪い絡みからこの人の音楽でしか味わえない美しさが立ち上がる①、ピアノではなくチェンバロを使用しその音色がハマりまくっている⑤、そして2つの楽器による音型の部分的反復が昨年の「Drifter」を思わせる⑥が好き。中でも⑥は美しすぎる。
【9】The International Nothing『In Doubt We Trust』
現代音楽。主に即興演奏の分野で活動するクラリネット奏者2人による特殊奏法などを活かした作曲作品。2つの(重音奏法なども用いているため時にはそれ以上の)音の重なりや完璧にコントロールされたうなりがとにかく美しい。オシレーターから発せられる電子音の扁平な持続や規則的な周期を持った音色の変化といった面を楽器演奏でトレースするような視点を強く感じさせるサウンドですが、人力の楽器演奏ゆえの音のパラメータのあるゆる部分における揺らぎもどうしようもなく混在していて、結果的に電子音とアコーステックな楽器音の境界をフラフラと行き交うような危ういバランスが独自の美しさを生み出す音楽になっています。重音奏法で音が重ねられる瞬間の音の立ち上がりや、一つの音程が抜けて隙間ができ他の音が違った距離感で聴こえてくる瞬間などそこかしこにハッとさせられるような場面がありますし、20分辺りからの比較的小さな音量でいくつかの音程が持続的に重ねられる場面なんかは、例えばJim O'Rourke『sleep like it's winter』における小音量のパートにも通じるような繊細な手触りが本当に素晴らしい。
【8】Utah Kawasaki『Restless Thoughtlessness』
電子音楽/実験音楽。90年代から活動している電子音楽家のユタカワサキによるアルバム。 “AlesisのMicronというデジタルシンセサイザのNRPN(機器固有のMIDIメッセージ)の非公開仕様を解析したページを参考に、設定可能なパラメータの値をすこしずつ変化させる([パラメータ数]個の次元を持つ空間の中を漂うような感じ)プログラムを実装し、それを実行して1時間放置したものを2セッション録音” したものとのことで、全くもって不規則に思える音の変形変質が、まるでその背後にいる知能の発する言語に聴こえてくるみたいなシリアスな誇大妄想感ある電子音楽。1時間の中で終盤のほうが音色が過激になってるような感じや、2つのテイクで音の発生の頻度や間に違いが聴き取れるように思うんですが、パラメータの数値の変化の方向性には何らかの制御が多少なりとも加わってるのかそれとも全くのランダムなのか気になるところ。新譜旧譜含めて2018年に聴いた作品の中で特に驚かされた作品がRoland Kaynの再発されたアルバム『Simultan』だったりするんですが、これは(アプローチは違うと思いますが)聴覚的にはそれに近く、瞬間的にはかなり恐さを感じる音であると同時にそこに異様に惹かれる感覚。モジュラーシンセの自動演奏にもライブコーディング系のパフォーマンスにも感じたことがない純粋な不定形であるが故の恐さというか。あとこれリンク先で読める山形一生さんの紹介文がすごく面白いです。
【7】今井和雄 & Roger Turner『Molecules』
即興演奏。日本のギタリストとイギリスのドラム奏者による共演作。2017年10月11日Bar Issheeでの2セットの演奏を収めたライブ録音。狭いスペースで、ガットギターと簡素な打楽器(+いくつかの物)というアコーステックな楽器演奏を近距離で捉えた録音のため残響成分などは最小限に抑えられ二人の演奏家の音のアタックやボリュームの操作がダイレクトに、手を伸ばせば掴めるような距離感で味わえる作品となっています。発されてはすぐさま減衰していく渇いた響きを様々に組み合わせ耳を刺激し続ける非常に巧みな演奏なんですが、特に驚くべきは今井和雄のガットギターの奏法/フレーズ/音響などあらゆる面における語彙の豊富さでしょう。特殊な器具などを用いるわけでもなく、持続音で数分間を横切るわけでもなく、左手で押弦して右手でピッキングするという基礎的な演奏の延長線上にある発音がかなりの割合を占めていると思いますが、ミュートのニュアンスやハーモニクスの使用を巧みに織り交ぜ、粒立ちのいい細かな音を間や密度を変えながら発し続ける様は30分超えの2セットを通して聴いても飽きることがありません。演奏の方向性として音数は非常に多いので、なんなら5分でネタ切れを起こしても全然おかしくなさそうですが……これだけでちょっと常軌を逸した凄みを感じます。テクニック的に秀でた演奏家がそれを発揮した演奏(いわゆる “ヴァーチュオーゾ” 的って言われるものとか)というのは様々な技法やサウンドがすぐにわかるレベルで次から次に繰り出される表面的な彩りが豊かなものを想像しがちですが、本作での今井和雄の演奏は様々な発音法やニュアンスで繰り出される音を聴いた結果としてガットギターという楽器が持つ逃れられない音の特性(例えば撥弦楽器特有の音の減衰感)をどうしようもなく意識させられるような、“音の細部(機微)” を文字通り鼓膜に押し付けられるような演奏だと感じました。こういう顕微鏡的な聴取を促される作品というのは音の間をたっぷりとって一音というものの存在感が否が応にも押し出される方向性をとったものなら多く思いつきますが、ここまで忙しない動きがあるもので初聴時からこれを意識させられた経験はちょっと記憶にないかもしれません。ロジャー・ターナーの演奏についてはやっぱ音量のコントロールがすごいですね。ガットギターの演奏に対してここしかないみたいな地点に本当に見事に収まり続けながらたまーに逸脱する感じ。ガシャガシャやっててもギターの響きを全然殺さないですし、楽器の “音量” という部分が空間の中で適切に噛み合い続けることが、それだけで演奏としての素晴らしさにこれほどまでに直結するものだとは正直なところ知らなかったです。2018年はインプロの作品で自分にとって新たな視点をもたらしてくれる作品にいくつか出会えたのですが、本作はギターとドラムという編成での(同じく2018年に初めて聴いたAndrea Centazzo & Derek Bailey『Drops』に並ぶ)フェイヴァリットであることと、複数人によるアコーステックな楽器演奏における音量の噛み合いの重要性を実感として教えてくれたことの二点で記憶に残るものとなりました。特に後者はこれからアコーステックな楽器演奏を聴く際には最重要といってもいいくらに強く意識させられる視点になると思います。
*ちなみに私が聴いたのは録音を担当した松岡さんより送っていただいたマスタリング前のデータ(24bit/96khz)です。CDではダイナミクスなどの面で多少異なった内容になっています。
【6】Thomas Ankersmit『Homage To Dick Raaijmakers』
電子音楽/ノイズ。ベルリンやアムステルダムを拠点に活動するアーティストのThomas Ankersmitによる、オランダのテープミュージックのパイオニア的存在の作曲家Dick Raaijmakersへのオマージュ作品。これまでの彼の作品と同じく、その代名詞ともいえるサージ・モジュラーシンセを中心的に扱った電子ノイズ作品なんですが、これまで以上にわかりやすく耳障りな音色の使用が多い印象。正直ここまでノイズ然とした作品を出してくるとは思ってなかったです。使用機材やトータルタイムなどで今作と通じる部分が多い2014年リリースの前作『Figueroa Terrace』は、ダイナミクスがかなり広く取られ展開や音色の重ね方も即興的に感じられる部分が多く、ノイジーな音響を多く取り入れながらも随所でアコーステックな楽器演奏のフィーリング(彼はサックスの演奏家でもあります)を感じさせる作品だったように思いますが、今作はダイナミクスはやや狭まり、プリミティブというかむき出しの電子音といった感じの粗っぽい音色の印象とは裏腹に展開や音の重ね方は細かな編集/コラージュが行われているように聴こえ、電子音でのみ可能な質感の音色を多く用い電子音楽ならではの手法(=編集)で構成された作曲作品というものを強く志した仕上がりに思えます。まあ端的に言うとオマージュが捧げられているDick Raaijmakersのこの曲なんかにかなり直接的に近い感じの作風ともいえるんですが、個人的には同じ時期によく聴いていたこともあって80年代半ば辺りのメルツバウの作品にも通じる強度を感じるコラージュ・ノイズ作品みたいな受け取り方もしたりしました。
*作品のキャプションにはInner-ear phenomena(内耳現象?)が関与している作品のためスピーカーで聴いてとの記載があり、たしかに随所で現れる音の持続が前面化したパートなんかはスピーカーに対する頭の角度によって聴こえ方がわかりやすく変わる感じはありますが、ヘッドホンやイヤホンで聴いてもその効果が多少オミットされるくらいでノイズ作品として聴くぶんには大きな問題はないかと思います。まあかなり耳にキツい音色がダイレクトにくる場面もあるので大音量で何度もとかはおすすめはしませんが。
5~1
【5】Leon Vynehall『Nothing Is Still』
ラウンジ/クラブ/エクスペリメンタル。UKのエレクトロニック・ミュージックのプロデューサーでありDJのレオン・ヴァインホールの初のフルアルバム。ディープハウスやダウンテンポをはじめ現代的なブーミーなサウンドも織り交ぜつつ、それらをストリングスやたゆたうようなシンセで纏い、硬派なエレクトロニック・ミュージックとしてもアーバンなラウンジミュージックとしても機能するような絶妙なバランスに辿り着いています。個々のトラックを抜き出して聴くとどれも一定のクオリティはあるもののそんなに騒ぐほどのものでもない気がするんですが、通して聴いた時のストーリー性のある流れが本当に最高。曇り空や雨の日に聴くと(それこそMassive Attack『Protection』並に)めちゃくちゃハマる感じがあって、雨のちらつく中の長時間運転中に繰り返し聴いてたら本当にこのまま消えてしまいたくらいに感動してしまいました。割といろんなエレクトロニック/クラブミュージックの語彙が入ってる辺りやアルバム全体での流れで魅せるようなところはDJとしての視点がすごく活きてる作品って感じがします。2018年は自分の観測範囲でUKジャズの盛り上がりがかなり目や耳に入った年だったんですが、その盛り上がりの起こり方だったり、Leifur James『A Louder Silence』なんかのいろんなジャンルのサウンドを自然に同居させる作品の在り方だったりからはUKにおいての様々な文化の交流の場としてのクラブの存在に思い馳せられ、この作品もまた同じような場から生まれ出てきたものなのだろうと強く感じさせられます。
【4】Jana Winderen『Spring Bloom in the Marginal Ice Zone』
フィールドレコーディング/サウンドスケープ。ノルウェー出身のサウンドアーティスト、ヤナ・ヴィンデレンによる作品。彼女はハイドロフォンを用いての海中調査、音の採取を長年続けているアーティストで、それによって得られた種々の音源を用いたサウンドスケープ作品を継続的にリリースしています。本作も同様のアプローチで、他作品と音が採取された場所やその採取のプロセスは異なるのかもしれませんが、聴覚上はかなり近しい印象。大雑把に言ってしまうとどれ聴いても一緒ともいえそうですが(多分ブラインドテスト的なことしたら聴き分けられないと思います)、毎回新しいの聴く度にその瑞々しい響きに目が覚めるほど引き付けられます。加えてこれまで以上に音の奥行きや空間性の豊かさを感じさせるミックスや音質の良さがあって聴いてて本当に一音一音の響きがうっとりするほどに素晴らしい。フィールドレコーディング作品というとちょっと渋いイメージかもしれませんがこれは音響的にかなり面白い音色が満載なので、例えばモジュラーシンセで奔放に生成される電子ノイズを聴くみたいな感覚でも楽しめると思います。音色を楽しむ音楽としての面白味や強度は相当なものがあります。ヘッドフォン用とスピーカー用のミックスが収録されてるってのも珍しいし興味深いですね。音が採集された場所や発音源、またその環境に関するステートメントがリンク先に記載されているので聴く際は是非合わせて目を通してみてください。
【3】Eli Keszler『Stadium』
ニューヨークを拠点に活動するパーカッショニスト、作曲家、ヴィジュアルアーティストによる作品。自身が演奏する多彩な打楽器といくつかの鍵盤楽器、更に曲によってトロンボーン、バグパイプ、チェロ、声などのゲスト奏者を迎え制作されています。基本的にはソロ多重録音+α的な認識が可能なバランスで、この辺りは前作『Last Signs of Speed』から地続きといった感触ですが、今作は鍵盤楽器や音階を奏でられる打楽器、ゲストによる演奏など音階を持ったフレーズの存在感が強くなることでいわゆるパーカッション・ミュージック的な様相はやや後退、淡い色合いで奏でられるハーモニーやメロディー(のようなもの)の中をアブストラクトなリズムが泳ぐという人力エレクトロニカ?とも言えそうなバランスの音楽になっています。この辺りのハーモニーやメロディーの存在とパーカッション・ミュージックとしての色合いのバランスは個人的には前作があまりにも好みだったため、本作には最初正直なところ戸惑いつつすこしガッカリといった感じだったんですが、何度か聴くうちにこのバランスもこれはこれでいいなと思えるようになり、結果かなりの回数繰り返し聴いてました。この人の演奏の最大の特徴である非常に細かで粒立ちのいい音を忙しなく発するドラミングが、淡いハーモニーなんかのサウンドと合わさると不思議な静謐さや浮遊感みたいなのが生まれてて、これだけ叩いておきながらグルーヴ・ミュージックというよりむしろアンビエント・ミュージックみたいに聴こえてくる時間も結構あって聴けば聴くほど風変わりなバランスの音楽に思えてなんかめっちゃクセになります。前作はそのあらゆる要素が今の自分にバチッとハマるこれぞ傑作って感じだったんですが、これはまだすごく惹かれるけど上手く言語化できないみたいな部分が結構ある(ゆえにまだまだ飽きずに何度も聴きたくなる)段階かもしれません。前作を手に取ったのが8月のパーカッション特集を書く段階だったってこともあって、10月リリースの本作と合わせて2018年の後半はこの人の音楽を本当によく聴いてました。なので前作の評価(マジで傑作です)も上乗せしてのこの順位って感じですかね。
【2】Louis Cole『Time』
エレクトロやジャズの技法をいかしたポップミュージック。LA在住のSSW/マルチ楽器奏者ルイス・コールの作品。これに関しては普段あまり聴かないジャンルってこともあって語る言葉をあんまり持ってないんですが、そういうジャンル分けでいう門外漢にも強烈に訴えてくるメロディーの素晴らしさ、完全にそれだけで持っていかれるアルバムって感じでめっちゃリピートしてました。1曲目冒頭の奇抜な音色の電子音に代表されるようなアレンジ面での遊び心は随所に感じられるんですが、それらが聴き手の感性をいたずらに引っ掻き回すような感じがなくて、メロディーへの没入をどんどんドライブさせるような効果を発揮してるのが最高ですね。マジでどの曲も口ずさみたくなるレベルでメロディーに乗せられてしまいます。技法的高度さを持った歌モノって展開の複雑さやメロディーの音程の上下動の多い、ともすれば聴き手を振り回すようなものになりがちだと思うんですが、この作品はそれを本当に見事に回避できてる点が心底気に入ってしまいました。繰り返しになってしまいますが口ずさみたくなる=一緒に歌いたくなるっていう事実が全てを物語ってる気がします。全曲好きなうえで特に好きなのは本当に気分でコロコロ変わる感じですが今は④「Phone」かなあ。
【1】Jim O'Rourke『sleep like it's winter』
ジム・オルーク流のアンビエント(への批評としての)作品。こちらの記事の最後のほうでも書いてますが、Steamroomでも発表されているようなジム・オルークの電子音を中心的に扱ったひと繋がりの長尺の音楽作品には個人的に、(1)音色やダイナミクスにおけるアコースティック楽器に近しい非常に繊細かつ有機的な操作、(2)時には無音を挟んだり、非常に小さな音量まで落ち込んだ状態でのクロスフェードなども用いる場面の移り変わり、(3)自動的に生成変化を行うシステムを構築することで作り出していると思われる時にノイズのようだったり、時に現代音楽のようだったりする複雑さや不和な感触を持った音響のうねり、といった点で比類なき素晴らしさがあると思っていて、そういったポイント(特に(1)と(2)かな)が特に美しいかたちで結実しているのが本作といえるかと思います。中でも(1)の部分、アコーステック楽器の響きのニュアンスやその演奏感覚を電子音楽の領域にここまで巧みに美しく取り込んだ例というのはちょっと他に聴いたことがなくて、音の立ち上がりや消失、持続の中での微かな手触りの変化といった部分の繊細な操作には聴く度に心底感動を覚えます。ごくごく個人的なアンビエント・ミュージックの重要な定義のひとつとして “抽象的な音楽であること” といったポイントがあって、ちょっと言語化が難しい部分ではあるんですが説明を試みるなら楽曲を最初から最後までフレーズや展開の単位でしっかり記憶できてしまうような楽理的構造の固さがあって、なおかつそこがその音楽の中心的な力点になっているもの(なので例えば音響の変化に焦点を当てるためフレーズを最小限の単位でしか扱わない、ミニマル寄りのアプローチのものは除く)というのはあまりアンビエントに聴こえないっていうところがあるのですが、本作はそういった点では記憶に残る部分と残らない部分が絶妙な割合で混在しつつ、音楽全体の手触りや印象は記憶に定着するという正に抽象性を持った音楽で、自分としてはアンビエント・ミュージックの定義にもの凄くしっかりハマる音楽性だと感じました(この点はそれこそ個人によって解釈や感覚が全然異なってくると思いますし、本作が全くもってアンビエントに聴こえないって方もいると思います)。Steamroomを全作聴くなんて面倒なことをやろうと思ったのも、本作の持つ魅力を少しでも深く知りたいと思ったからですし、それくらいの手間や時間をかけて接する価値のある本当に素晴らしい音楽作品だと思います。11、12月辺りはSteamroomと本作をはじめジム・オルークの音楽ばかり聴き、そのことばかり考えていてましたね。未だに聴く度に新たな発見がありますし、これから間違いなく数えきれないほど繰り返し聴く作品になるでしょう。
プレイリスト
ストリーミングには半分くらいしかなかったですが……。
Spotifyとは曲のセレクトを変えてます。