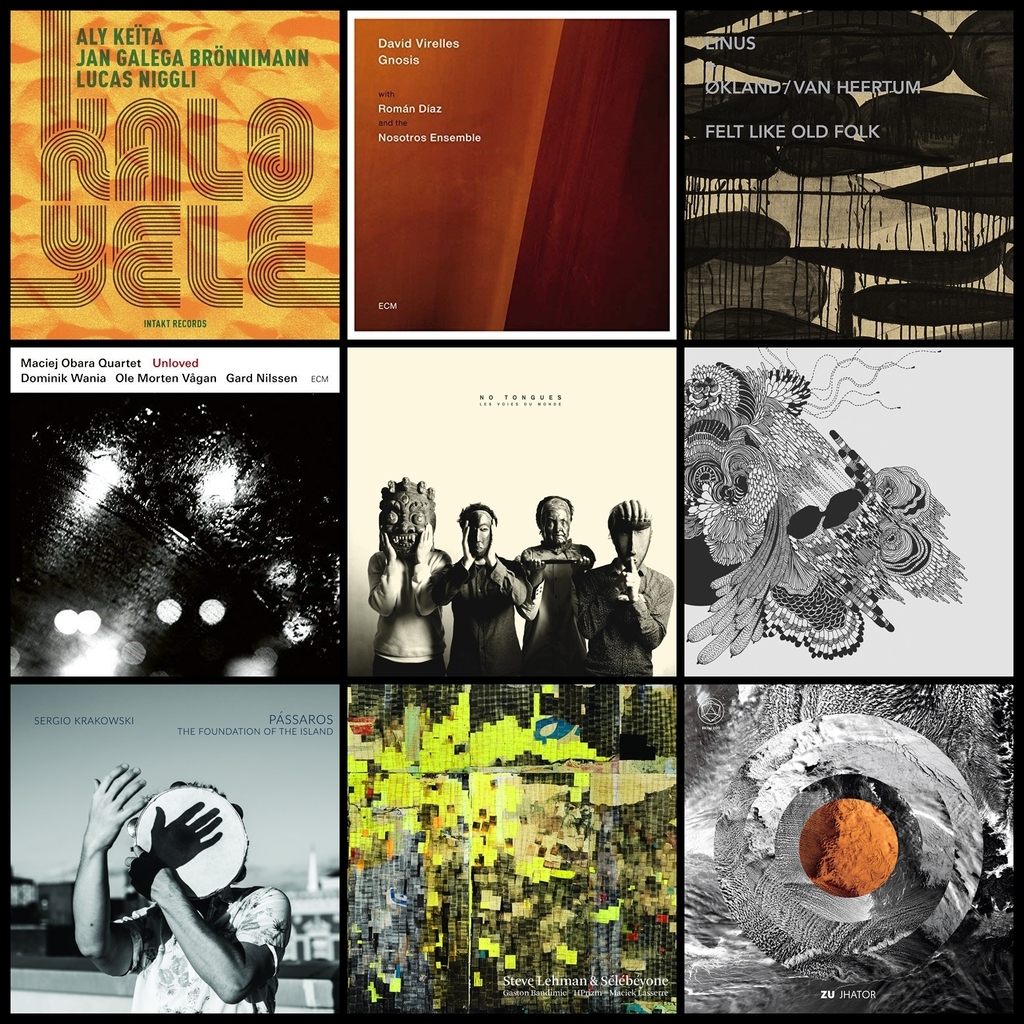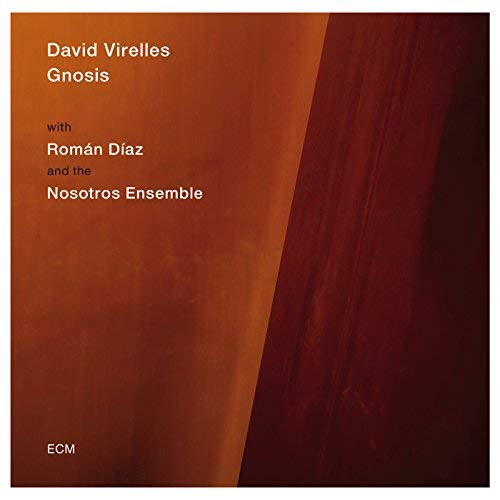Tyshawn SoreyのCD3枚組に及ぶ新作『Pillars』のそれぞれのパートについて、その見通しを測るため楽器編成や場面の移り変わりに対する短い記述をしていきます。
「Pillars I」
楽器編成:
ドラムやパーカッションなどの打楽器はおそらくほとんどをTyshawn Soreyが演奏
ギターはセンターに位置しアコースティックとエレクトリックが用いられるが同時に鳴ることはなくおそらくどちらもTodd Neufeld
コントラバスは左右とセンターにおそらく計4本 左右に1本ずつ、真ん中に2本が位置しているが、真ん中の2本については片方のみが音を出す場面も多いように聴こえる(判別が難しい)
センターに位置する2本のコントラバスのうち1本はエレクトロニクスでの発音も行っているためCarl Testaだろう
管楽器は右にトロンボーンのBen Gerstein、左にトランペットのStephen Haynes(場面によってはフリューゲルホルンなども演奏していると思われる)
センターでエレクトリックギターとエレクトロニクスを用いたコントラバスが同時に鳴る場合その判別が難しい
センターでエレクトロニクスとコントラバスの音が同時に鳴っている場合、電子音はコントラバスの音をライブサンプリングしたもの(つまり演奏者は一人)との認識で書いているが、もしかしたらそれぞれ個別の演奏者が出しているのかもしれない。
i) 00:00~
スネアのロールからスタート
ii) 03:56~
ギターとドラム/パーカッションのデュオ
iii) 15:47~
コントラバス4本による、おそらくある程度作曲されたパート
途中から弓弾きによる長い音の重奏がメインとなりコーラスがかかったような持続音を聴かせる
21:40辺りからトランペットやギター(更に遅れてトロンボーン)も演奏に加わる それぞれの楽器が即興的に演奏しているように聴こえる
このパートでの4本のコントラバスは左右の2本が指弾きで和音を短く奏で、真ん中の2本は弓弾きによる持続音を出すことが多い
iv) 31:10~
コントラバスの音が退きトランペットとトロンボーンが残る 即興のデュオ
36:40辺りからギター、コントラバスが演奏に加わり集団即興的な場面へ ギターはノイズや雑音的な演奏 真ん中に位置するコントラバスもエレクトロニクスで音色を加工しているように聴こえる
40:20辺りで真ん中のコントラバスのみが残りソロ演奏へ エレクトロニクスを大胆に用いたエフェクティブな演奏
v) 42:15~
コントラバスがエレクトロニクスを切りアコースティックな独奏へ移行
vi) 48:56~
ギターの独奏
vii) 52:02~
ギターの演奏にコントラバス、トロンボーン、打楽器が徐々に色を滲ませるように加わってくる
いつの間にかギターは退きトロンボーンと打楽器が前面へ
57分辺りからコントラバス3本が弓弾きで加わる 不穏なハーモニーを形成するがその中に時折調和の取れた穏やかな響きも忍ばせる
60分のタイミングで再びギターが演奏に区切りをつけるように入り、鼓のような打楽器の音も鳴らさる
その後はコントラバスと管楽器(トロンボーンとフリューゲルホルン?)が長い音を中心としたやりとりを行う
viii) 63:54~
エレクトロニクスの高音が入り銅鑼のような音で場面が転換
打楽器がまばらに鳴らされる中でトランペット、ギター、真ん中のコントラバス、の順番で演奏に加わり緊張感のある即興演奏へ
ix)71:00~
コントラバスの弓弾きが入るのを合図に演奏の趣が穏やかに
ゆらゆらと歩みがスローダウンするように演奏の速度感が落ち着いていく
x) 73:05~
一転して管楽器が厚みのある響きを繰り出し ギター、打楽器なども騒がしさを感じさせる演奏で加わる
遅れて真ん中のコントラバスも加わり管楽器が引き続き演奏する不穏なトーンで幕引き
「Pillars II」
楽器編成:
基本的には「Pillars I」と楽器の定位など変わりはないと思うが、
ii)のギター2本のデュオパートの際にははっきり右にJoe Morris、左にTodd Neufeldと振り分けられている
以降のパートでJoe Morrisがギターを演奏することはなく、センターの位置からコントラバスが2本聴こえる(つまり左右と合わせてコントラバス奏者が4人になっている)場面があるように思うので、ii)以降のパートではジョー・モリスはコントラバスを演奏していると推測する
vi)のパートのアコースティックギターはセンターに定位されている これはおそらくTodd Neufeld
ところどころでコントラバスが3本なのか4本なのか判別が難しい
i) 00:00~
コントラバス2本によるデュオ演奏 おそらく即興
ii) 05:30~
ギター2本によるデュオ 右がJoe Morris、左がTodd Neufeldか ここも即興だろうが二人の違いがよくわかる
iii) 15:14~
エレクトロニクスのノイズが入り場面が転換 パーカッションも入りデュオ的な演奏へ
少し遅れてトランペット、更に遅れてメロディカ、少し間を置いてトロンボーン(メロディカからの持ち替え)も演奏に加わる
メロディカが入るタイミングでバスドラムをマレットで叩いたような打音が一定の間隔を置き鳴らされる
演奏は徐々に音の強さやスピード感を増していく 特にそれをわかりやすく感じさせるのが打楽器の演奏
25分過ぎ辺りで一度打楽器が抜け浮遊感のあるような時間が短く訪れる
その後演奏は徐々に落ち着き非常に静謐なものに
音量が落ち切ったところでエレクトロニクスを演奏していたCarl Testaがコントラバスでいくつかの音をポツポツと鳴らす
iv) 29:56~
鈴のような音、続いてトロンボーンの2音からなるフレーズとバスドラムの強打が繰り返し鳴らされる
何らかの管楽器(左から聴こえるのでStephen Haynesによるコルネット、またはアルトホルンか? 音域から推測するとTyshawn Soreyの担当楽器にクレジットされているdungchenという管楽器である可能性が最も高いようにも思う)による独奏となり濁った低い持続音がブレスの間を置きつつ鳴らされ続ける
それがしばらく続くと前のパートでも聴かれたバスドラムをマレットで叩いたような打音が入り一定の間隔を置き鳴らされ続ける
更にコントラバス(おそらく3本とも)が非常に低い音域の弓弾きで加わる
以降は管楽器、コントラバスの持続音とバスドラムの打音によるドゥーミーなドローン的な演奏がパートの終わりまで続く(Tony Conrad with Faustの演奏をピッチダウンさせたもののように聴こえなくもない)
他に鳴らされる音はまばらに演奏される打楽器類くらいか
v) 44:17~
コントラバスの音が途切れ鈴のような音のみが鳴る
センターのコントラバスが指弾きで入り打楽器類とのデュオのような場面へ
遅れてトランペットが控えめに演奏に加わる
更に遅れて徐々に他のコントラバスやトロンボーンも演奏に加わってくる
最終的にコントラバスは3本または4本鳴っているように思うがどちらかは聴き分けが難しく現状断定できない
途中から右のほうで鳴る管楽器の裏返ったような高い音域の雑音っぽい音は誰がどの楽器で発しているのかもよくわからない
各楽器が非常にまばらに鳴る即興といった感じだが不思議な流れのよさが感じられ心地いい
vi) 56:54~
センターでアコースティックギターが鳴らされる(演奏はおそらくTodd Neufeld)のを合図に次の場面へ
ギター、左側のコントラバス(途中からセンターのものも入る)、打楽器、トロンボーンがまばらに音を発し合う演奏 どこか音の渡し合いのようにも聴こえる
ギターは延々同じ和音のみを爪弾き、コントラバスはゆっくりと単音を指弾きで
打楽器はゴングやシンバル、スネア、タムなどが中心か
トロンボーンは他の楽器の音を渡し合うような振る舞いからやや自由でソロ的な演奏にも聴こえる
このパートの演奏は『That/Not』に入っているものとの近似を強く感じる
vii) 71:35~
管楽器が濃厚なトーンを響かせドラムも騒がしく演奏する重厚感のあるフィナーレ
鳴らされる管楽器のクレッシェンドする単音のフレーズは「Pillars I」と同一のもので最終的な幕の引き方も同様
「Pillars III」
楽器編成:
基本的には「Pillars I」「Pillars II」と変わりはないが、
2本のギターが左右で鳴る場合「Pillars II」では右がJoe Morris、左がTodd Neufeldだったが「Pillars III」では逆になっている
ここまでと同じく鳴っているコントラバスの本数が3本なのか4本なのか判別し難い場面があるが、IIIにおいてはジョー・モリスがギターを演奏している場面が比較的多いので3本である可能性が高いのではと推測する
iii) のパートで鳴らされ続ける非常に低い音を発する管楽器が誰の演奏するどの楽器なのかがしっかりとわからないが、音域などから推測するとTyshawn Soreyの担当楽器にクレジットされているdungchenという管楽器である可能性が高いのではと思う
だがこの場合その音が鳴っている時間に鳴らされる打楽器類の音はTyshawn Sorey以外の演奏者が演奏していることになる?(オーバーダビングを用いたり、管楽器を固定して演奏し空いた手で打楽器を演奏している可能性も考えられるが)
i) 00:00~
3本のコントラバスとギターが交互に音を発するミニマルなパート
コントラバスは冒頭から弓弾きを続けるが3:30辺りで左右のものは一旦指弾きに移行
4分辺りでトロンボーンが入る コントラバスとギターの音のやりとりには関わらずソロ的に自由に演奏する
ii) 09:02~
トロンボーンの独奏
iii) 12:10~
打楽器が入り派手に場面が転換
管楽器(左側から聴こえるためStephen Haynesが演奏する何らかの楽器の可能性もあるが音域から判断するとTyshawn Soreyの担当楽器にクレジットされているdungchenという管楽器ではないかと思う)の非常に低い音が入り独奏となる 同音程のロングトーンを繰り返し発するミニマルなもの
少し経つと打楽器が控えめに演奏に加わり、更に遅れてコントラバスも非常に低い音域の持続音で加わる
途中から “II” の4つめのパートのようにバスドラムをマレットで叩いたような打音が一定の間隔を置き鳴らされるが、こちらでは合間に別の打楽器の強打が挟まれる
パートの2/3を過ぎた辺りで管楽器の音が退く 更に打楽器の音も止みコントラバスの持続音が中心となる
その後トロンボーンが入り打楽器も演奏を再開 トロンボーンは非常に高い音域(フラジオ音域?)で濁った音色を出すなど非常に特殊な演奏を行う
コントラバスの持続音はパートの終わりまで続く ここでも鳴っているのが3本なのか4本なのかは判別が難しい
パートの最後ではシンバルの大胆なクレッシェンドが入り高圧的なサウンドへ
パート全体を通して “II” の4つめのパートに非常に近いドゥーミーなドローン的な演奏といえる
iv) 31:55~
打楽器による独奏
マレットによる柔らかい打音を響かせる演奏が中心で静謐さを感じさせる
徐々に音数が増え固い打音も用いられる
低い音域で膨張するように鳴る倍音をいかした演奏が行われるため再生環境によってはだいぶ印象が異なるものになってしまうかもしれない(特にイヤホンでは厳しいかも)
v) 41:05~
ギター2本によるデュオ
右がTodd Neufeldで左がJoe Morrisだと思うが、左側の演奏もなんだかとてもTodd Neufeldっぽく聴こえるような……
途中から打楽器やトランペットも加わる
抽象的ながらも終始どこかメロウさを感じさせる演奏が行われる
vi) 49:48~
静かに打楽器とトロンボーンのデュオへ移行
ここでもトロンボーンは非常に高い音域で痙攣するような音を発したり声を混ぜた吹奏を行うなど非常に特殊な演奏をしている
54分辺りで真ん中のコントラバスが演奏に加わる 安定したピッチを発せず音程がエフェクティブに動くブランコがゆっくり揺れる様子を思わせるような演奏
更にトランペットと左右のギターも演奏に加わる
57:47から打楽器が騒がしく打ち鳴らされ演奏の速度が上がる
“I” と “II” を含めたここまでで最も騒がしく喧騒を思わせるような集団即興に突入する
集団即興はトランペットとトロンボーン、2本のギター、打楽器で行われこのパートの途中で演奏に参加していたコントラバスはそういった場面に突入してから(トランペットやギターが演奏に参加した辺りから)は音を発していないと思われる
トロンボーンによる割れた音色のトーンが数回激しく鳴らされこのパートは終わる
vii) 65:25~
アコースティックギター(演奏はTodd Neufeldだろう)と左側のコントラバスによる即興のデュオ
viii) 71:40~
トランペットとトロンボーンによる演奏
同じ音程の繰り返しを基調にメロディーの演奏も織り交ぜ柔らかい印象を与える
ix) 73:40~
ギターの叩きつけるような発音と鼓を思わせる打楽器の乱打で一転して不穏な雰囲気に場面が転換
“I” や “II” と同じく管楽器のクレッシェンドする単音のフレーズが表れ騒がしさや重厚さを感じさせるフィナーレへ
“I” や “II” と同じく管楽器のフレーズで幕引き